当社が担当しています!
AUTOMOBILE
私たちが携わる、 先端自動車開発技術の一部をご紹介!クロップス・クルートヨタ事業部は、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)の核心技術に携わり、高い専門性を発揮しています。
ここでは、当社の主要な技術分野の一端をご紹介します。
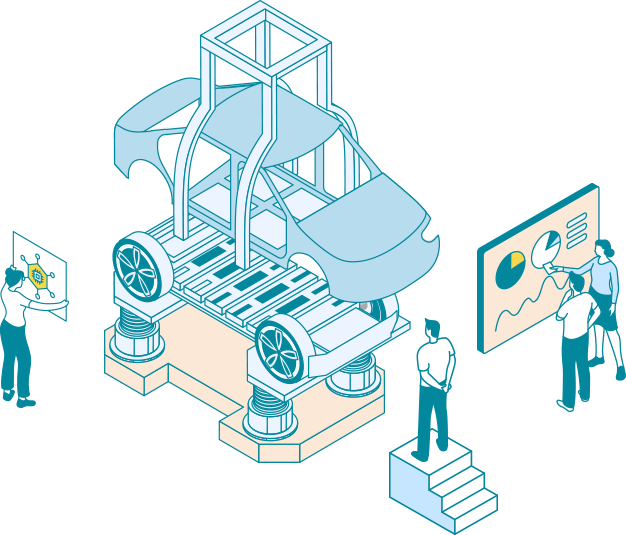
PCU PCU PCU設計開発
EVの動力源、
PCUの開発を担っています!
当社が担当しています!
開発の流れ

| 01 | 「電気仕様設計」 バッテリー、モーターへIN/OUTする電気をどのように制御するか検討します。 |
|---|---|
| 02 | 「構造設計」 PCUを構成する各部品をPCUの箱のどこに配置するか検討します。 |
| 03 |
「搭載設計」 |
エンジニアの声

「PCUの機能設計を担当しています。机上計算はもとより熱/流体解析や回路シミュレータなどの解析ツールを使って機能設計を行います。設計した仕様は車の性能(燃費や加速性能、乗り心地など)に反映されるので、担当した車が燃費性能1位になったときが嬉しいです。」

「私が担当するのは、PCUの電気仕様設計業務。設計という名がつきますが、図面を描いたりモデリングをするのではなく、電気回路の仕様を決めることに重点を置いています。PCUの機能や性能に関する考え方を整理し、システム検討や解析を行う大切な役割を担っています。」
MOTOR EVALUATION MOTOR EVALUATION モーター評価技術
クルマを動かす動力を解析!
HVの4WDモデルはFR(前)、RR(後)に1つずつ、
合計2つのモーター(デュアルモーター)が
付いていることが一般的です。
開発の流れ
| 01 | モーターの設計要件を把握します。 |
|---|---|
| 02 | その要件を基にモーター実機による評価(実験)を行います。 |
| 03 | 評価から得られるデータを解析し、設計要件と照らし合わせOK/NGの判断を行います。 |
エンジニアの声
 「トヨタ自動車のEV・HV開発部署に所属し、NV領域を担当しています。NV(Noise Vibration)とは音・振動のことで、私の業務はモーター・インバーターの振動騒音試験を実施し評価することです。エンジン車からEV・HVへの移行が進む中、新たな技術課題に貢献できることがやりがい!より静かで快適な走行環境の実現に向けて尽力しています。」
「トヨタ自動車のEV・HV開発部署に所属し、NV領域を担当しています。NV(Noise Vibration)とは音・振動のことで、私の業務はモーター・インバーターの振動騒音試験を実施し評価することです。エンジン車からEV・HVへの移行が進む中、新たな技術課題に貢献できることがやりがい!より静かで快適な走行環境の実現に向けて尽力しています。」
AUTOMATIC GUIDED VEHICLE AUTOMATIC GUIDED VEHICLE AGV導入
工場自働化のカギ、
AGV(無人搬送車)
生産ラインの効率化を目指す
重要な役割を担っています。
物流改善業務では既存の設備や自動搬送機
といった物流システムを理解した上で、
工事計画者として、工場の省人化を進めています。
田原工場のAGV導入は「クロップス・クルーが
すべて担っている」といっても過言ではありません!
現在ではその働きが認められ、
他工場からも依頼を受けるようになりました。
AGV導入の流れ
| 01 | 設備、自動搬送機、構成図、プログラムなど既存システムを把握します。 |
|---|---|
| 02 | できあがっている仕組みに対して、類似工程への横展や無人化できる工程を計画し、改善を提案します。 |
| 03 | 仕入れ先や現場のスタッフと連携しながら、物の渋滞を避けるなど、効率的な物流システムを構築します。 |
エンジニアの声
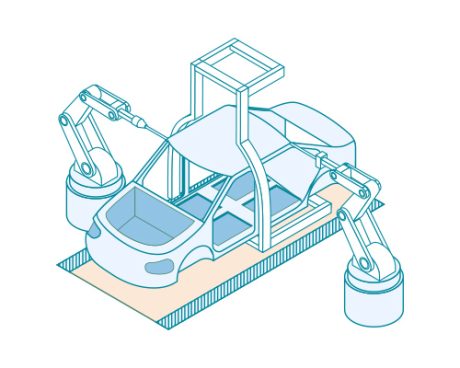 「生産ラインへの部品搬送を有人から無人にしつつ、物の流れの整流化も見極める必要があります。
「生産ラインへの部品搬送を有人から無人にしつつ、物の流れの整流化も見極める必要があります。
せっかく導入しても物が渋滞していては意味がありませんので、ここが難しいポイントです。
実際は自身が操作するわけではありませんが、仕入れ先様、職場の皆さんに気持ちよく仕事をしてもらうために仕様を考え、つくり込むことにやりがいを感じています。
実際にできあがった状態を目の当たりにすると嬉しく思います。」
PROJECT PROJECT 開発ストーリー
プロジェクトの成功事例の数々!
ほんの少しご紹介します。

Story.01 設計開発
eAxle開発プロジェクト
「インバーターの小型化への挑戦」
eAxle内のインバーターをできるだけ小さく、低く、軽くすることに挑戦しました。インバーターの位置が車両の形状や性能に大きな影響を与えるため、この課題は非常に重要でした。
複数の車種に搭載されるインバーターは、多くの部署からの要望を聞いて設計することが求められます。そこで、情報を整理し、各要求を慎重に検討しながら設計を進めました。
苦労の末、最終的に複数の車種に適合し、かつコンパクトで軽量なインバーターの開発に成功。この成果は、現在注目を集めているBEV(バッテリー式電気自動車)試作車の製作プロセス確立にもつながっています。
eAxleは「電動アクスル」とも呼ばれ、電気自動車(EV)や電動車の駆動システムの中核となる重要な部品です。従来の「エンジン+トランスミッション」に代わる電動車の駆動ユニットとして機能します。

Story.02 プロジェクト推進
カムリ・プリウスなどの
生産管理プロジェクト
「予期せぬ問題との闘い」
新製品開発のプロジェクト管理において、一番大変なのは「調整」です。特に設計や製造段階で発生する問題は日常茶飯事で、その都度調整会を繰り返す必要がありました。
例えば、ある海外車種のプロジェクトでは、ローカルメンバーとのコミュニケーションに苦心…。後工程で関わる工場や色々な仕入れ先にご協力いただきながら、頻繁な調整会議を行いプロジェクトを前進させていきました。
たくさんの関係者たちのおかげで、市場に製品を送り出すことができた時の喜びは格別でした。街中で携わった車を見かけると、チーム全体の努力が実を結んだことを実感できます。

Story.03 生産技術
部品物流検討及び
改善業務プロジェクト
「3D-CADによる物流の見える化」
新車種追加に伴って部品荷姿(輸送する際の荷物の外観)や供給方法が変わってくるため、既存部品と新部品の両立が求められます。この部品物流検討に対し、3D-CADを活用したアプローチを導入しました。
車種ごとに異なる部品荷姿や供給方法を3D-CADを用いて事前検討するノウハウを学び実践。その結果、物流検討時間の大幅な短縮を実現しました。さらに、他の業務に充てる時間も確保できるようになりました。
この3D-CADによる物流の見える化を、工場の製準部署メンバーにも継承。これにより、部門全体の業務効率が向上し、より迅速で正確な物流計画の立案が可能になりました。

Story.04 実験評価
次世代インバーター
開発プロジェクト
「謎のノイズを特定せよ」
開発中の車両からインバーターのノイズが発生し、チームは原因特定に奔走!何度も試験走行を繰り返し、どのような走行条件でノイズが発生するかを徹底的に調査しました。
ノイズの周波数、モーターの回転数、トルクなど、膨大なデータを測定・分析。
地道な作業の末、ようやく原因を特定することができました。
原因判明後は、関係部署と緊密に連携し、ハードウェアとソフトウェアの両面から対策を実施。この経験から、車の走り方によって、さまざまなノイズが発生することがわかり、より広範囲の試験の導入へと繋がりました。同じ問題を繰り返さないためのシステム作り、世の中に製品を出しても問題ないかどうかの評価導入など、現在の業務に幅広く貢献できていると思います。
